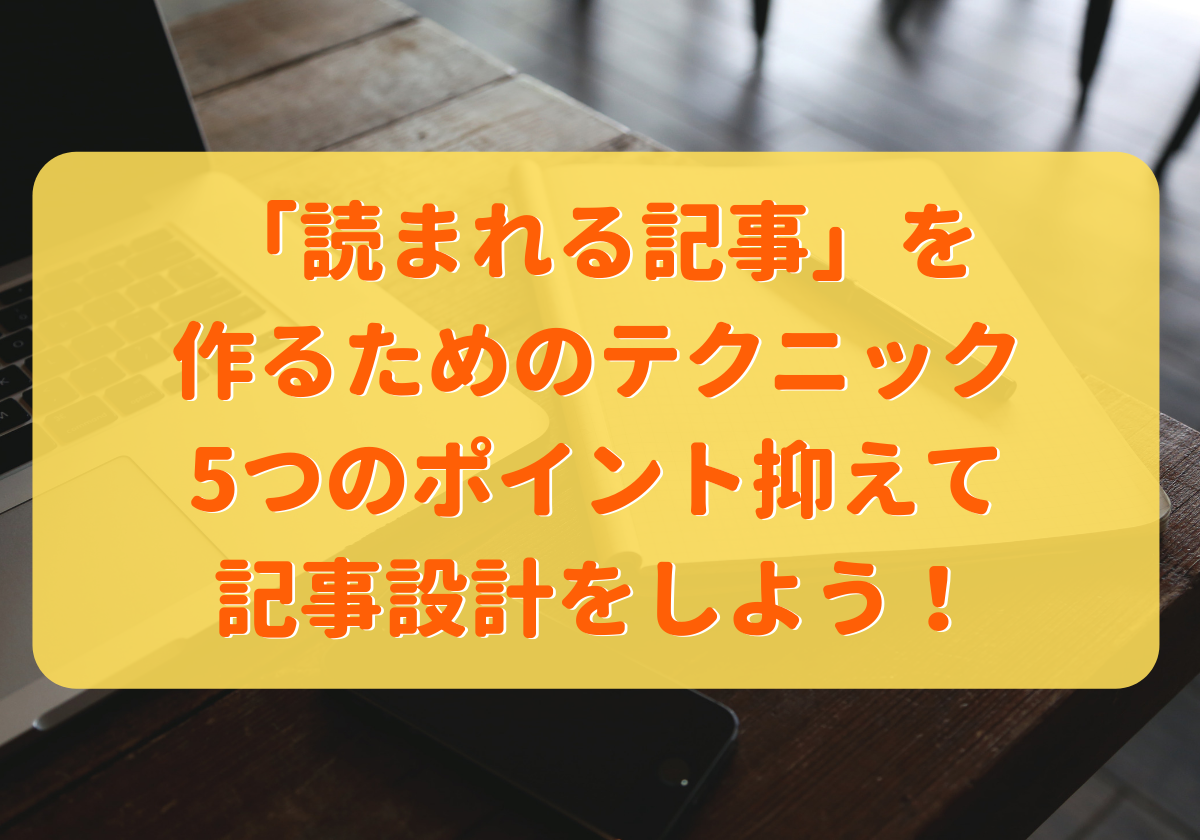
「ブログを書いていてもなかなか読まれない」
「以前よりも記事が読まれるようになった」
2019年3月コアアップデート以降ブログの変化は悲喜交々です。
僕のブログも「読まれる記事」と「読まれない記事」の両極化しています。
ではどうすれば読まれる記事を作れるのか?
読者ファーストを目指すためのポイントは準備にあります。
5つのポイントを押さえて準備しましょう!

「読まれる記事」を作るためのテクニック。5つのポイント抑えて記事設計をしよう!
こんにちは、あまかず(@amakazusan)です。
今回は読者に向けての記事を作る方法です
コアアップデートにより両極端になった記事達

2019年3月コアアップデートにより、「読まれる記事」と「読まれない記事」が両極端になってきました。
読まれる記事は今まで通りたくさんの人に読まれ、
読まれない記事はアクセスは激減もしくは検索にも引っかからなくなりました。
コレは僕のブログの中で起きていることです。
しかし、結構な人の中で同じような事が起きているのではないでしょうか?
「読まれる記事」と「読まれない記事」の違いとは?

では、読まれる記事とは読まれない記事の違いとはなんなのか?
端的に言えば
「読者に求められているか、否か」
コレにつきます。
今日は週末以上にブログへのアクセスがある。
まぁ、理由はわかってるんですよ。
読者が知りたいページにアクセスが偏ってる。Googleが読者ファーストと言ってる以上、
「〇〇に行ってきました」
「〇〇だと思います」
と言うような個人的な発信ではよっぽどの事が無い限り検索には見向きもされない— あまかず@ノートの人・ブログのアニキ (@amakazuganma) April 11, 2019
僕自身、読まれている記事は「読者が知りたい情報」を書いた記事なんです。
では、どんな記事が読者に求められるのか?
それのポイントはここです。
- 読者の疑問を解決できるか?
- 読者の知りたいを満たすことができるのか?
以前こんな記事を書きました。
この記事では「自分の提供出来る物=読者の求める物」となったときに読まれる記事になる。
もちろん自分のいいたいことや書きたい事があるのは当然です。
しかし、これらからはそれを踏まえつつ「読者が求める物」に変換していく作業が必要になってきます。
読まれる記事を作るための記事設計

では、どうやって「自分がいいたいことを言いつつ、読者が求める物」を記事に反映させて行けばいいのか?
その秘訣は書く前の準備にあります。
以前から僕は書く前の準備が大切と言ってきました。
書く前に読者がどんな事を望んでいるかを考えて記事設計をする。
この記事設計がポイントです。
ただ、注意したいのが闇雲に記事設計をしても意味はありません。
以下の順番で記事設計をしていくとかなりやりやすくなります。
記事設計のポイント
- 各記事の目的は何か?
- 誰に伝える記事なのか?
- 読者の知りたい事は何か?
- この記事で一番言いたいことは何か?
- 読んだ結果どうなるのか?
各項目を1行程度の文章にしていくと記事の方向性が見えてくるはずです。
それぞれ解説していきます。
各記事の目的は何か?
最初にするのは「記事の目的」を考える事。
記事を闇雲に書き出すのではなくまずどんな記事を書くのか?
目的地をハッキリさせます。
それによって記事のブレが減る事になります。
これは簡単にきめる程度でいいです。
詳しくきめなくてもあくまでこんな記事にしたい程度でOKでたす。
例)たまたま立ち寄ったやきとん屋さんが良かったので記事にしたい。
こう言う場合の目的は「やきとん屋さんを紹介する」という感じでOKです。
誰に伝える記事なのか?
続いて考えるのが「誰に向けて」です。
記事を書く以上誰かに向けて書きます。
つまり、記事のターゲットを決めます。
友人だったり、知人だったり、ペルソナを決めてもいいかもしれません。
個人的に一番手っ取り早いのが「過去の自分」です。
過去の自分は読めませんが、同じ境遇の人は必ずいます。
その人に向けて記事をかきます。
例)結構いいやきとん屋さんだったのでもっと早く知っていたかった。
というこでここは「過去の自分」をターゲットにします
読者の知りたい事は何か?
3つめにやることは、2で決めた読者が「知りたい事は何なのか?」コレを考える事です。
もちろん実際に読者の求めている事がわかる訳ではありません。
想像や妄想の力をフルに働かせて読者の知りたいを考えます。
ターゲットが過去の自分だとわかりやすいですよね。
自分が何を求めて検索するのか?それを考えます。
例)ターゲットである「過去の自分が」どうしたらそのやきとん屋さんの何が知りたいのか?
やきとんの種類なのか?メニューなのか?お酒の種類のなのか?ボリュームなのか?
いろいろ考えられますよね。
この記事で一番言いたいことは何か?
4番目は読者の知りたいを考えたら、
その知りたいに応えられるような「自分の意見」を考えます。
読者に伝えたくて、自分のいいたいことを決めます。
例)今回伝えたいのは「串一本当たりの肉が大きくて食べ応えがあった!」ということ。「レバー」も美味しかったので伝えたい。
読んだ結果どうなるのか?
最後に考えるのがこの記事を読んだ読者がどうなるのかを考えます。
- 何を得するのか?
- 何を知る事ができるのか?
この辺を考えてあげるとどんな事を書けば良いのか記事の全体像が見えてくるはずです。
例)きっとこの記事を読んだ僕は絶対興味が出てお店に行きたくなるはず!
こんな感じでOKです。
記事設計の例

説明の中で例を挙げましたが、それを元に記事設計をすると以下の様な形になります。
- 各記事の目的は何か?
→たまたま行ったやきとんの店が良かった! - 誰に伝える記事なのか?
→過去の自分に伝える - 読者の知りたい事は何か?
→どんなやきとんやメニューがあるのか? - この記事で一番言いたいことは何か?
→串一本当たりの肉が大きくて食べ応えがあった!特にレバーは美味しい。 - 読んだ結果どうなるのか?
→紹介したやきとん屋さんに行きたくなる。いろんな人がお店に足を運んで人気が出て欲しい。
上記の5つのポイントをノートやスマホ・PCのメモ帳に書き出しておくといいですね。
書きだしているとだんだんと記事の輪郭が見えてくるはずです。
例を元に実際記事設計を書いた記事がコチラです。
記事設計をすると記事に書く内容が見えてくる
書く前に記事設計をするといいことはたくさんあります。
- どんな情報を書けば良いのか?
- 何を伝えればいいのか?
- どうかけばいいのか?
これらが明確になってきます。
明確になっていればあとは何を書けば良いのかを考えて書くだけ。
設計した記事に併せて実際の記事を書いていけば「読まれる記事」ができあがっていきます。
自分の事を語りつつ読者が知りたい事を書く

実際の会話でもそうですが、
話し手の自分語りを一方的に話すのを聞くのってどうしても嫌ですよね。
興味があって話を聞くのであってその人の語りをずっと聞いていたい訳ではありません。
ブログでもそうなんです。
読者のいかに知りたい事をいかに提供できるか?
これが読まれる記事のコツなんです。
Googleも「読者ファースト」とずっとそう言ってきました。
読者が求める物や知りたい事を書くと言うことも必要になってきます。
もし、自分が読まれていないのであれば一度自分の記事を振り返って見る必要があります。
まとめ
記事を書く前に「記事設計」をしよう
ポイントは以下の5つ
- 各記事の目的は何か?
- 誰に伝える記事なのか?
- 読者の知りたい事は何か?
- この記事で一番言いたいことは何か?
- 読んだ結果どうなるのか?
書く前に是非ためしてみてください。
今日のポイント
以上、読まれる記事を作るためのポイントでした。
僕もこの考えを取り入れてから飛躍的に記事が上達してきました。
なので「読者」を考える事は大切なんです。
こう言うと「自分の主張は無視するのか!」と言われそうですが、そうではありません。
もちろん「自己の主張」も大切です。
ただ、「読まれる記事」と「自己主張の記事」は別物だと言う事を覚えておいてください。
この辺は近いうちに記事にしていきます。お楽しみに。

あわせ読みたい関連記事
■2019年3月コアアップデートで数字が落ちた。ブロガーである以上書くしかない
■リライトしてますか?過去記事を活かすために必要な4つの作業
ブログのライティングに参考になる本
■スポンサーリンク■

